ゾンビ
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年2月) |

ゾンビのイラスト
ゾンビ(英語: Zombie)とは、何らかの力で死体のまま蘇った人間の総称である。ホラーやファンタジー作品などに登場し、「腐った死体が歩き回る」という描写が多くなされる。
目次
1 現実におけるゾンビ
1.1 起源
1.2 伝統的な施術
1.3 ゾンビ・パウダー
1.4 実情
1.5 比喩としてのゾンビ
2 架空世界におけるゾンビ
3 参考画像
4 脚注
5 関連書籍・参考文献
6 関連項目
7 外部リンク
現実におけるゾンビ
起源
「生ける死体」として知られており、ブードゥー教のルーツであるヴォドゥンを信仰するアフリカ人は霊魂の存在を信じている。こちらについては「目に見えないもの」として捉えている。
「ゾンビ」は、元はコンゴで信仰されている神「ンザンビ(Nzambi)」に由来する。「不思議な力を持つもの」はンザンビと呼ばれており、その対象は人や動物、物などにも及ぶ。これがコンゴ出身の奴隷達によって中米・西インド諸島に伝わる過程で「ゾンビ」へ変わっていった。
伝統的な施術
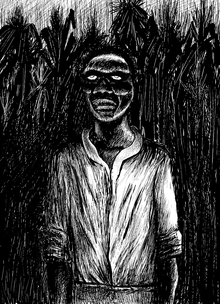
ハイチのゾンビのイラスト
この術はヴードゥーの司祭の一つであるボコにより行われる。ボコの生業は依頼を受けて人を貶める事である。ボコは死体が腐り始める前に墓から掘り出し、幾度も死体の名前を呼び続ける。やがて死体が墓から起き上がったところを、両手を縛り、使用人として農園に売り出す。死体の魂は壷の中に封じ込まれ、以後ゾンビは永劫に奴隷として働き続ける。死人の家族は死人をゾンビにさせまいと、埋葬後36時間見張る、死体に毒薬を施す、死体を切り裂くなどの方策を採る。死体に刃物を握らせ、死体が起き出したらボコを一刺しできるようにする場合もあるという。
もちろん、名前を呼ばれて死体が蘇るはずもなく、農民達による言い伝えに過ぎない。現在でも、ヴードゥーを信仰しているハイチなどでは、未だに「マーケットでゾンビを見た」などの話が多い。また、知的・精神的障害者の様子がたまたま死者に似ていたケースを取り上げ、「死亡した人がゾンビ化される事例がある」などとされることもある。
ゾンビ・パウダー
実際にゾンビを作るにあたってゾンビ・パウダーというものが使用される。ゾンビ・パウダーの起源はナイジェリアの少数民族であるエフェク人やカラバル人にあるとされる。西アフリカ社会では伝統的な刑法としてこの毒が用いられており、これが奴隷達により西インド諸島に持ち込まれた。一般に、「ゾンビ・パウダーにはテトロドトキシンが含まれている」と言われている。この毒素を対象者の傷口から浸透させる事により仮死状態を作り出し、パウダー全量に対する毒素の濃度が丁度よければ薬と施術により蘇生し、濃度が高ければ死に至り、仮死状態にある脳(前頭葉)は酸欠によりダメージを負うため、自発的意思のない人間=ゾンビを作り出すことが出来る。ゾンビと化した人間は、言い成りに動く奴隷として農園などで使役され続けた。
これらは民族植物学者、ウェイド・デイヴィスが自著[1]で提唱した仮説であり、実際は事実に反する事項や創作が多く、例えばゾンビ・パウダーに使われているのはフグの仲間であるハリセンボンと言われるが、ハリセンボンはテトロドトキシンを持っていない。また、テトロドトキシンの傷口からの浸透によって仮死状態にするという仮説には無理があるとの指摘もある。
実情
「ゾンビ化」とは、嫌われ者や結社内の掟を破った者に社会的制裁を加えるための行為であり、この場合の「死者」とは生物的なものではなく、共同体の保護と権利を奪われる、つまり「社会的な死者として扱われる」ことであると、ゾラ・ニール・ハーストンやアルフレッド・メトローなどの人類学者は、ゾンビに関する研究の早い時期から論じていた[2]。
イギリス人の人類学者、ローランド・リトルウッドはハイチに渡って詳細なるデータを取り、ゾンビの存在を全否定している。1997年に、「マーケットに死んだはずの息子がゾンビとなって歩いていた」と言ってふらふら歩いている人物を自宅に連れ帰った父親の報告があり、その息子とされた人物を医学的に検査したところ、死んだ形跡が全くなかった。また、その人物には知的障害があり、DNA検査によって父親と親子関係のない他人の空似だったことが判明した。その他も同様に、他人の空似のケースばかりであったことが報告されている。
2011年には、アメリカ戦略軍において地球全体がゾンビに襲われるシナリオでの軍事作戦の訓練テンプレート「CONOP8888」が作成されている。これは架空シナリオを実際の軍事計画と勘違いしないよう、ありえないゾンビが敵として想定されたという[3]。
比喩としてのゾンビ
- 実行終了中のプロセスを「ゾンビプロセス」と呼ぶことがある[4]。
- 保守が終了済みにもかかわらず使い続けられるオープンソースソフトウェアを「ゾンビOSS」と呼ぶことがある[5]。
超新星爆発を二度も起こした星を「ゾンビ星」と呼ぶことがある[6]。
サバイバルゲームで被弾したことを申告せずにゲームを続ける人を「ゾンビ」と呼ぶことがある。
架空世界におけるゾンビ
 メディアを再生する
メディアを再生する映画史における最初のゾンビ映画『恐怖城』(White Zombie)
映画史における最初のゾンビ登場は、1932年の『恐怖城』(ビデオ化名「ホワイトゾンビ」)と古い。この映画に登場するゾンビは、後年の映画における「生きる屍」ではなく、ゾンビパウダーにより仮死状態にされた人間でゾンビマスターの命令に常に忠実で、人を襲うことも人肉を食らうこともない。
1960年代中盤までゾンビの登場する映画は多数作られたが、主たる悪役はあくまでも邪悪な魔道士であり、ゾンビ自体は脇役である。そのため、吸血鬼や狼男、ミイラといった恐怖映画の主役と比べ、マイナーな存在であった。
現行のゾンビ像を決定づけたのは、1968年のジョージ・A・ロメロのアメリカ映画『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』である。この作品でロメロはブードゥー教のゾンビに吸血鬼の特徴を混ぜ込み、「生ける死体」を作りあげた。
ロメロのゾンビには吸血鬼的要素の「ゾンビに殺された人間もゾンビ化する」という設定が追加されたため、「人類よりも増える一方のゾンビの方が多いという終末的な状況下で、なんとか生き延びようともがく人々、そして人間同士の浅ましい争い」を描く作品となることが多い。このスタイルの原点は、リチャード・マシスンによる終末SF『地球最後の男』である。同作は「吸血鬼による人類の滅亡と主役の交代」というプロットだが、『ゾンビ』においては「やがて全生物が死滅し、最終的に地球は死の星となる」とされている。
近年では呪術や魔法的な手法ではなく、科学実験や特殊なウイルス感染、あるいは寄生虫によりゾンビ化するという設定がある。これらの作品には、パンデミックという形で被害が拡大するパニック物の様相を呈するものも多い。
マイケル・ジャクソンのPV『スリラー』では、マイケル率いるゾンビに扮したダンスチームがダンスを行っている。
参考画像

ゾンビのメイク

疫病や生物兵器などによる終末ものフィクションの中には、ゾンビもしばしば登場する
Night of the Living Dead (1968) theatrical poster.jpg
現行のゾンビ像を決定づけた『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』
脚注
^ ウェイド・デイヴィス(Wade Davis)「蛇と虹 (The Serpent and the Rainbow)」(1985年)
^ 今福龍太「国家システムによる死者の管理は、かならずやゾンビに報復される」『死体の本』宝島社、1995年。
^ 米国防総省、「ゾンビ」襲来の対応策を策定していた CNN 2014年5月17日
^ “Linuxキーワード - ゾンビ・プロセス”. ITpro (2007年7月30日). 2017年11月17日閲覧。
^ “[1]オープンソースソフトウエアにも寿命がある”. ITpro (2015年3月23日). 2017年11月17日閲覧。
^ “爆発後に何度もよみがえる「ゾンビ星」が観測される”. WIRED.jp (2017年11月18日). 2017年11月18日閲覧。
関連書籍・参考文献
- 『新・トンデモ超常現象60の真相』皆神龍太郎 志水一夫 加門正一 楽工社 ISBN 4903063070
- 『蛇と虹―ゾンビの謎に挑む』ウェイド・デイヴィス草思社 ISBN 4794203136
- 『ゾンビ伝説―ハイチのゾンビの謎に挑む』ウェイド・デイヴィス第三書館 ISBN 4807498169
- 檀原照和 『ヴードゥー大全』 夏目出版 2006年
関連項目
- ゾンビによる世界の終末
キョンシー / ミイラ
- 死人憑
- 帝国アハト刑
ゾンビ映画の一覧 / 「オブ・ザ・デッド」で終わる作品の一覧
- カテゴリ:ゾンビを題材としたフィクション作品
外部リンク
Zombies and p-Zombies (英語) - Skeptic's Dictionary「ゾンビと哲学的ゾンビ」の項目。- ゾンビの正体を暴け!(特命リサーチ200XII File No.0725)



