社会学
| 社会学 |
|---|
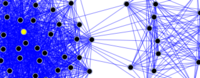 |
一般的な側面 |
社会学史 - 実証主義 領域: 小児 - 文化 |
関連分野および隣接分野 |
カルチュラル・スタディーズ 社会言語学 - 社会福祉学 |
社会学(しゃかいがく、英: sociology)は、社会現象の実態や、現象の起こる原因に関するメカニズム(因果関係)を統計・データなどを用いて分析することで解明する学問である[1][2]。その研究対象は、行為、行動、相互作用といったミクロレベルのものから、家族、コミュニティなどの集団、組織、さらには、社会構造やその変動(社会変動)などマクロレベルに及ぶものまでさまざまである。思想史的に言えば、「同時代(史)を把握する認識・概念(コンセプト)」を作り出そうとする学問である。
目次
1 概要
1.1 社会学の成立と実証主義の展開
1.2 古典的理論の形成
1.3 シカゴ学派の誕生
1.4 機能主義社会学の台頭
1.5 後期近代化と社会学の多様化
1.6 政策科学への流れと新たな理論形成
1.7 主な理論と方法論
1.8 社会調査
2 社会学の対象
2.1 主なテーマ
2.2 連字符社会学
2.3 隣接
3 関連書籍
4 学界報告・討論・論文寄稿軽視問題
5 脚注
6 参考文献
7 関連項目
8 外部リンク
8.1 学会組織
8.2 研究者個人運営サイト
8.3 データベース
8.4 その他
概要
社会学の成立と実証主義の展開

オーギュスト・コント
社会学([仏] sociologie = [羅] socius + [希] logos)なる用語は、フランス革命後の混乱と動乱に満ちた初期近代フランスを生きたオーギュスト・コントによって作られた。コントは、当時の産業主義と合理主義を背景として、社会学とは「秩序と進歩」に寄与する「社会物理学」であって、歴史学、心理学、経済学を統合する実証主義的な科学的研究でなければならないとした[3]。
このコントの思想は、その師であるサン・シモンに遡る。サン・シモンは、自然科学の方法を用いて社会的世界を全体的かつ統一的に説明する「社会生理学」の樹立を企てた。このなかで、サン・シモンは、フランス革命後の新社会の秩序を捉えるべく、その社会変動の流れを「産業主義」として提示した[4]。ここからコントはさらに、近代社会の構成原理として実証主義を提示し、産業ではなく科学をその中心に据えることになった。そしてその中心に社会学を位置づけたのである[5]。
コントらの発想は、ジョン・スチュアート・ミル、ハーバート・スペンサーなどに受け継がれ、実証主義の体系化がはかられていった。たとえば、スペンサーは、イギリス功利主義の考えと、彼独自の進化論に基づいて、有機体システムとのアナロジーによって社会を超有機的「システム」と捉え、後の社会システム理論の先駆となる研究を行なった[6]。
古典的理論の形成

マックス・ヴェーバー
実証主義の潮流のなかで始まった社会学であるが、19世紀末から20世紀にかけて、カール・マルクス、マックス・ウェーバー、エミール・デュルケーム、ゲオルク・ジンメル、ヴィルフレド・パレートらが、さまざまな立場から相次いで研究著作を発表した。その方法論、キー概念などは、形を変えながらその後の社会学に引き継がれており、この時期は、社会学の古典的理論の形成期にあたる。

エミール・デュルケーム

ゲオルク・ジンメル
デュルケームは、コントらの社会発展論(近代化論)を「社会分業論」として受け継ぎ、分業による連帯を「社会的事実の機能的なメカニズム」によるものとして説明する機能主義的な社会システム論を創始した。さらにデュルケームは、実証主義の伝統を継承し、自然科学の方法を社会科学へと拡大することを「社会学的方法の規準」の根底に据えた。しかし、実証主義は自然科学に対抗するような人文社会科学の方法論を打ち立てるものではなく、社会学の中心思想になることなく、ウェーバー、ジンメル、さらに後にはパーソンズらによって数々の批判を受けることになる。
ウェーバーは前世代の近代化論を「資本主義の精神」の理論として受け継ぎ、ジンメルは「社会分化」の理論として受け継いだ。両者は、ドイツ哲学の伝統に則り(自然科学一元論ではなく)新カント派的科学方法論に依拠し、方法論的個人主義を創始した。すなわち、ウェーバーの場合には理解社会学による行為理論を打ち立て、ジンメルの場合は、後のシンボリック相互作用論につながる形式社会学と生の哲学の視点から関係論的定式化を行ない、マクロ客観主義の限界を乗り越える方向へ進んだのである。
こうした、実証主義の伝統を引き継いだデュルケムの方法論的集合主義(社会実在論=社会的事実)と、主にウェーバーによる方法論的個人主義(社会唯名論)との対立は、後に、「社会システムの社会学」(マクロ社会学)と「社会的行為の社会学」(ミクロ社会学)として引き継がれることになった。また、社会学の認識については、価値自由のルールにのっとったものであるべきか、それとも「精神科学」の伝統に準拠した人文学的性格のものであるべきかという、実証主義と反実証主義の対立が生まれたが、これも後に、たとえば、批判理論と構造主義的マルクス主義のアプローチとして繰り返されることになった。
シカゴ学派の誕生

G.H.ミード
20世紀初頭まではヨーロッパにおいて社会学の主潮が形成されていたが、第一次世界大戦後にはアメリカ合衆国において顕著な展開を見せるようになり、やがてプラグマティックな社会学研究の中心として発展を遂げていくことになった。
アメリカ社会学が社会学研究の中心的地位を築き上げていく背景には、19世紀末から20世紀初頭にかけての急激な経済・社会の変化があった。南北戦争から第一次世界大戦へ至る半世紀の間にアメリカ産業は急ピッチな発展を遂げ、それに伴って都市化が進行し、民衆の生活様式も大きく変わっていった。このような大きく変貌を遂げるアメリカ社会の実態を捉えることが、社会学の課題として要請されるようになっていったのである。
当初、アメリカの社会学は、1893年に創設されたシカゴ大学を中心に、人種・移民をめぐる問題、犯罪、非行、労働問題、地域的コミュニティの変貌などの現象的な側面を実証的に解明する社会心理学や都市社会学が興隆していった。アルビオン・スモール、ウィリアム・トマス、ジョージ・ハーバード・ミード、ロバート・E・パーク、アーネスト・バージェス、ルイス・ワースら、有能な研究者たちの活躍によって、1920~30年代にシカゴ大学は、アメリカの学会において強い影響力を及ぼすようになり、シカゴ学派と呼ばれる有力な研究者グループを形成するまでになった。
ヨーロッパの社会学は観念的・方法論的側面を重視する傾向が強かったが、アメリカ社会学は現実の問題を解決する方向性を示すという実践的側面が強くみられる。この点は、実際的な有用性を重視するプラグマティズムの精神的な伝統によるところが大きく、また、前述のような社会的要請もあって、地域社会や家族などの具体的な対象を研究する個別科学としての傾向を持つようになった。
機能主義社会学の台頭
さらに、第二次世界大戦後のアメリカでは、タルコット・パーソンズやロバート・キング・マートンらによる機能主義が提唱され、社会学全体に大きな影響を及ぼした。とくにパーソンズの構造機能主義社会学は、社会学における統一理論を築き上げる意図を持って提起され、多くの社会学者に影響を与え、20世紀半ばにおける「主流を成す見解」と目されるに至った。これは分野の統一、体系化が実現するかに見えた社会学の稀有な時期であるとされる。
しかしパーソンズの理論は、その科学論的・政治思想的な構想があまりに遠大かつ複雑であったことから、正しく評価されていなかったともされており、また、合理的選択論のケネス・アローらが指摘するところによれば、パーソンズ自身が掲げた要求にしたがった理論形成もなされていなかった。また、1960年代以降には、「観念的傾向が強い」「現状の体制を維持しようという保守的傾向がある」「個人の非合理的な行為についての視点が欠けている」などといった数多くの批判ないし断罪を受けることになった。
いずれにせよ、パーソンズの社会システム論は、結局、統一理論構築にまではいたらず、以下に見るような、主にミクロ・レベルの視点に立った理論がさまざまな立場から提唱されるようになった。
後期近代化と社会学の多様化

ユルゲン・ハーバーマス
他方で、第一次世界大戦、第二次世界大戦の惨禍を眼前にしたヨーロッパ社会学では、理性信仰の崩壊とともに、西洋近代社会の構成原理そのものへの反省が生まれていた。そこで、機能主義の流れとは別に、ドイツでは、テオドール・アドルノやユルゲン・ハーバーマスに代表されるフランクフルト学派の批判理論、フランスでは、ルイ・アルチュセールらの構造主義的マルクス主義、ミシェル・フーコーの権力論が展開された。
これらの動きとともに、後期近代化への動きを背景として脱産業化論、紛争理論などが唱えられ、1960年代末には機能主義からの離反が決定的なものとなる。こうして、いわゆるミニ・パラダイム(この語法は本来は誤りである)の乱立と称される時代を迎える。以上の理論の他に、日常世界への着目から、シンボリック相互作用論、現象学的社会学、エスノメソドロジー、ピエール・ブルデューの社会学などが影響力を持つようになるとともに、ジェームズ・コールマンら方法論的個人主義の立場からは合理的選択理論なども唱えられるようになり、社会学が多様化し、研究対象となる領域も、たとえばジェンダーの社会学といった具合にさまざまに分化し拡大した。
ただし、この多様化によって、同時に社会学というディシプリン内部での対話の共通基盤が失われることにもなった。上述のような歴史的文脈が忘却されると、機能主義に対するカウンターとしての意義をもった諸ミニパラダイムは逆に混迷を深めた。一方で、(クーンが本来意図した意味での)パラダイム、すなわち経験的統計データに基づく調査研究は疑問視されることなく確立していったが、他方でかかる研究のよって立つべき思想・視点、つまりは社会学の独自性とは何なのかという問題が問われることにもなった。
政策科学への流れと新たな理論形成

アンソニー・ギデンズ
そのなかで、1960年代にパーソンズのもとに留学し、ドイツに帰国後、社会学者として活動を開始したニクラス・ルーマンや、1990年代末以降の英国ブレア労働党政権のブレーンとして名を馳せたアンソニー・ギデンズらは、それぞれ異なった系譜からではあるが、政策科学としての社会学という立場を打ち出した。
たとえば、ルーマンの場合であれば、科学的にSollen(~すべき)を言わなければならない行政学の伝統を継承する形で社会システム論を展開し、また、構造化論を展開したギデンズの場合は、社会問題への関与を続けてきたイギリス社会学の伝統とリベラリズムの政治思想への関わりから、そうした方向性をとり、それぞれに反響を呼び起こした。
また、政策科学への流れとともに、20世紀末になると、グローバル化、情報化、リスク社会化などを背景としつつ、社会構築主義の影響力が高まるなかで、構造化論、機能構造主義社会学も含め、従来の社会学における「社会」の自己再生産性の前提に対する疑義が高まり、「情報」や「メディア」、「移動」などを「社会」に代わるキー概念とした新たな理論構築も見られるようになっている。
主な理論と方法論
人間は、歴史社会を創造するとともに、歴史社会のなかを生きる存在である。社会学もまた、そうした人間の歴史的営為の二重性のなかにある。したがって、その理論と方法は、客観的に進展されるものではないが、前節に見られるような現実世界の変容のなかで、以下のような理論と方法論が主に展開されてきている。
- 総合社会学
形式社会学 - シカゴ学派 - シンボリック相互作用論 - ドラマツルギー
理解社会学 - 現象学的社会学 - エスノメソドロジー - 会話分析
- 知識社会学
- デュルケーム学派
- 比較社会学
数理社会学 - 社会的交換理論 - 合理的選択理論
構造機能主義 - 機能主義 - 社会システム理論
紛争理論(闘争理論)
構造主義的マルクス主義 - 批判的実在論 - 言説分析 - カルチュラル・スタディーズ
フランクフルト学派 - 批判理論
- フェミニズム
社会調査
経験社会学は、現実の社会からデータを取らなくてはならないため、さまざまな方法が考えられている。主として社会調査が用いられるが、調査の他に、実験、観察、内容分析(文書や映像資料等の分析)、マクロデータ(集計された統計データ)の利用などの手法がある。どれも一長一短があるが、それぞれが重要な研究手法である。
「社会階層と社会移動全国調査」(SSM調査)や、家族社会学会による調査など、社会学者による大規模な調査も存在する。統計数理研究所による日本人の国民性調査や、日本版総合社会調査(JGSS調査)なども存在する。SSM調査の成果は、米国で数冊の本が出版された他、韓国や中国でも翻訳が出版されており、国際的にも高く評価されている。例えば原純輔・盛山和夫による『社会階層』は韓国、中国、米国で出版されている。
米国の社会学においては、公開されている既存の社会調査データが多いこともあり、大規模なデータファイルの計量分析をもとにした計量社会学が、近年では非常に盛んである。アメリカ社会学会の機関誌 American Sociological Review (ASR)も論文の7割前後が計量分析を用いた論文である。実験や観察、質的調査による研究、理論研究などもあるが、最近はやや沈滞気味で数は多くはない。米国では理論だけの研究はほとんどなく理論と実証の往復が重視される。質的調査は米国において1990年代以前に小規模な流行があったが、米国では社会学における科学主義や実証主義の考え方が強いためあまり重視されず、とくに2000年以降は研究は少ない。[要出典]
社会学の対象
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年5月) |
主なテーマ
社会学の主たる研究テーマの一つは、秩序問題、すなわち社会秩序や、何らかの社会への協力行動と関連した問題群である。具体的には、治安や犯罪、逸脱行動、地位/役割、権力/支配関係、利他的行動、社会的ジレンマなどが問題にされる。また、社会心理学や小集団実験と関連する研究も多い。とりわけ近年では、社会的な包摂/排除や治安・犯罪に関わるテーマが世界的に注目されている。数理社会学や合理的選択理論の手法を用いた研究も盛んになっている。
こうしたミクロ・レベルでの秩序問題の解明とともに、マクロな社会構造とその時代的変化、すなわち社会変動の分析も、社会学の主要なテーマである。たとえば、産業社会や労働市場、社会階層、学校システム、家族や地域社会、国家社会などの構造や問題構制の変容過程などである。これらの分野では、社会システム論による総合的な理論蓄積のほか、大規模な調査データを元にした個別的な研究成果も多く挙がっている。
社会変動研究は、もともと近代主義的、発展段階論的な視点によるものが多かったが(マルクス主義社会学もその一つに数えられよう)、実際の資本主義社会の変容(たとえば脱産業社会化)や隣接学問分野の動向を見据え、今日では、そうした古典的研究の批判的継承のもとに(たとえばポスト・マルクス主義社会学)、さまざまな社会現象とその変化に関する解釈学的(=歴史的)、構築主義的な研究が広く行われている。
高度経済成長期以降の日本の社会学でも、やはり産業社会化、都市社会化、大衆社会化といった近代化に伴う社会変動が主として扱われてきたが、最近では、脱産業化、少子高齢化、情報テクノロジー化、ネットワーク化、グローバル化などによる社会的、物質的変容に焦点を据えた研究が取り組まれるようになっている。
連字符社会学
社会学が対象とする領域は幅広いため、特定の分野を扱う連字符社会学(カール・マンハイムの命名による)が大量に発達することになった。その分野の歴史や他の学問への影響、方法論などはさまざまである。以下は連字符社会学の実例。
- 医療社会学
- エスニシティの社会学
- 音楽社会学
- 科学社会学
- 家族社会学
- 環境社会学
- 感情社会学
- 教育社会学
- 軍事社会学
- 経営社会学
- 経験社会学
- 経済社会学
- 言語社会学
- 国際社会学
- 産業社会学
- ジェンダーの社会学
- 社会学の社会学
- 宗教社会学
- 情報社会学
- スポーツ社会学
- 政治社会学
- 青年社会学
- 組織社会学
- 地域社会学
- 知識社会学
- 都市社会学
- 農村社会学
- 犯罪社会学
- 文学社会学
- 文化社会学
- 法社会学
- 臨床社会学
- 歴史社会学
- 労働社会学
- 老年社会学
隣接
- 社会経済学
社会言語学 - コミュニケーション論 - 社会情報学
- 社会心理学
- 社会病理学
- 社会階層論
- 社会ネットワーク論
行動科学 - 社会統計学
- 社会福祉学
関連書籍
出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2015年5月) |
(古典・教科書・啓蒙書)
- マックス・ウェーバー『社会学の根本概念』(岩波文庫, 1972年)
- エミール・デュルケム『社会学的方法の規準』(岩波文庫, 1978年)
- アンソニー・ギデンズ『社会学の新しい方法的規準 第二版』(而立書房, 2000年)
- アンソニー・ギデンズ『社会学 第五版』(而立書房, 2009年)
(講座・シリーズ)
- 『リーディングス 日本の社会学』全20巻(東京大学出版会, 1985-7年)
- 『岩波講座 現代社会学』全26巻+別巻1、井上俊、上野千鶴子、大澤真幸、見田宗介、吉見俊哉編(岩波書店, 1995-7年)
- 『講座社会学』全16巻、北川隆吉、塩原勉、蓮見音彦編(東京大学出版会, 1998年-)
- 『講座 社会変動』全10巻(ミネルヴァ書房, 2001年-)
- 『社会学のアクチュアリティ』全12巻+別巻2、武川正吾、友枝敏雄、西原和久、山田昌弘、吉原直樹編(東信堂, 2004年)
(翻訳シリーズ)
- 『現代社会学大系』全15巻、日高六郎、岩井弘融、中野卓、浜島朗、田中清助、北川隆吉編(青木書店, 1970年- ※復刻版有)
- 『社会学の思想』全15巻、長谷川公一、藤田弘夫、吉原直樹編(青木書店, 1999年-)
(辞書)
新明正道編『社会学辞典』(河出書房, 1944年)〔復刻・増補版〕(時潮社, 2009年)- 森岡清美、塩原勉、本間康平編『新社会学辞典』(有斐閣, 1993年)
- 見田宗介他編『社会学事典』(弘文堂, 1994年)
- 浜島朗他編『社会学小辞典』(有斐閣, 1997年)
- 見田宗介他編『社会学文献事典』(弘文堂, 1998年)
宮島喬編『岩波小辞典社会学』(岩波書店, 2003年)- ブードン他『ラルース社会学事典』(弘文堂, 1997年)
レイモンド・ウィリアムズ『キーワード辞典』(平凡社, 2004年)
(国内総合雑誌)
- 『社会学評論』(日本社会学会, 1950年刊)
- 『社会学研究』(東北社会学研究会, 1950年刊)
- 『ソシオロジ』(社会学研究会, 1952年刊)
- 『ソシオロゴス』(ソシオロゴス編集委員会、1977年刊)
(国際総合雑誌)
American Journal of Sociology (1895年刊)
American Sociological Review (1936年刊)
British Journal of Sociology (1950年刊)
Sociological Inquiry (1961年刊)
学界報告・討論・論文寄稿軽視問題
太郎丸博京都大学大学院文学研究科教授は以前から著書で学会報告や学会誌などアカデミズムを軽視している日本の社会学の研究者、教授・学界そのものを批判している。日本社会学学者らは学会誌への論文・投稿学会で自身の研究を発表せず、様々なマスコミによって「社会学者づらして本を出版したり、さまざまなメディアで発言することができる」のが実状だと指摘している。「先生」扱いされる日本の社会学者らは他者からの批評されるのを恐れて、第三者から査読を受けない上に、学会誌には必ず投稿しないと告発している。更に太郎丸は売上しか気にしない出版社も研究の水準や主張の真偽も確認しない問題も指摘している。太郎丸は彼らを見て育った大学院生たちも、彼らのように学会報告や学会誌というアカデミズムを軽視し、本に好き勝手なことを書くことを社会学者の理想だと誤解するため、研究成果をほとんど出さない人が日本の社会学者の多数になっていると警告している。社会学者同士の議論が日本の社会学界にはないと指摘している[7][1]。
脚注
- ^ ab“阪大を去るにあたって: 社会学の危機と希望 | 太郎丸博Theoretical Sociology” (日本語). Theoretical Sociology. 2018年10月8日閲覧。
^ 人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門p18 2005 太郎丸博
^ 清水 (1978) などを参照のこと。
^ 富永(2008: 31-68)
^ 富永 (2008: 73-107)
^ 富永 (2008: 185-216)
^ 人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門p159 2005 太郎丸博
参考文献
清水幾太郎 (1978) 『オーギュスト・コント――社会学とは何か』(岩波書店[岩波新書], 1978年)
富永健一 (2008) 『思想としての社会学』(新曜社, 2008年)
関連項目
- 社会学者の一覧
- 社会学部
- 社会学史
- 日本社会学会
- 社会調査士
- 反社会学講座
- 社会哲学
- 社会思想
- 社会史
- 学術出版
外部リンク
学会組織
- 日本社会学会
International Sociological Association (ISA)
研究者個人運営サイト
ソキウス - 社会学者・野村一夫による。
データベース
- 社会学文献情報データベース
SSJデータアーカイブ(データファイルの入手)
その他
社会学講話(1907年)国立国会図書館
社会学理論の発展はいかにして可能かPDF
| ||||
